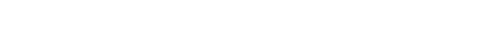横光利一の小説「赤い着物」を読んだ考察と感想
横光利一は文学の神様といわれるほどの作家です。
横光利一は最初の妻が病気にかかってしまい大変に苦労しました。妻との闘病を描いた作品としては、「春は馬車に乗って」や「花園の思想」などがあります。
新感覚派の小説家として川端康成と並んで高い評価を受けています。
私は小説家ですが、横光利一の影響を強く受けました。今回は私が好きな横光利一の小説「赤い着物」の感想文を記事にします。
独特の文体で構成される世界

横光利一作品の特徴として独特の文体が挙げられます。
師匠である菊池寛の流れも受け継いでいるのですが、文章の一つ一つが美しいのです。太宰治が最も得意としたのは女性独白体という文体なのですが、太宰治はイメージを固めて一気に書き上げてしまうという特性を持っていました。
これに対して、芥川龍之介は、文章を削り取っていき精選された文章にしていくという特性を持っていました。
横光利一も芥川龍之介と新感覚派の小説家として、文章の一つ一つが精選されています。例えるならば、余分な脂肪をそぎ落とした筋肉質の体型の文体のようなものです。
「赤い着物」においても、横光利一の最大の魅力である文体の美しさが遺憾なく発揮されています。
村の点燈夫(てんとうふ)は雨の中を帰っていった。火の点(つ)いた献灯(けんとう)の光りの下で、梨の花が雨に打たれていた。
上記の一文からは、雨の情景の美しさが瞳の奥によみがえり、横光利一が描き出す世界の美しさに心がつつまれていきます。
村の点燈夫(てんとうふ)は雨の中を帰っていった。
点燈夫(てんとうふ)とは点燈に明かりをつけてまわる人のことです。この人が「帰っていった」から、この人はもう用事をすませたことがわかります。では、点燈夫(てんとうふ)はどんな用事をすませたのでしょうか?
「火の点(つ)いた献灯(けんとう)の光り」が必要なので、この雨は暗がりの中の雨であることがわかります。そんな暗がりの中で「梨の花が雨に打たれて」いるのです。
活気よく灸の姉たちの声がした。茶の間では銅壺(どうこ)が湯気を立てて鳴っていた。灸はまた縁側(えんがわ)に立って暗い外を眺めていた。飛脚(ひきゃく)の提灯(ちょうちん)の火が街の方から帰って来た。びしょ濡れになった犬が首を垂れて、影のように献燈の下を通っていった。
上記の文章を読んでいくと、家の情景、庭の情景、家の外の情景とスムーズに情景描写が移動していき、読む人の心をとらえていきます。
また、注目すべき表現としては、下記の一文です。
びしょ濡れになった犬が首を垂れて、影のように献燈の下を通っていった。
「影のように」は、横光利一の文体に多用されている比喩表現の一種なのですが、こちらの文を読めば、犬が影を引き連れて献灯の影を通り過ぎているということもイメージされます。つまり、直接的に情景を描くのではなく、間接的に情景を描写するという手法も横光利一の誇るべき文章技術なのです。
私はこのような横光文学の美しさに心を打たれて、横光利一の作品に没頭することとなったのです。横光利一の師匠である菊池寛も比喩法を多く使う文体なのですが、横光利一の比喩法は美しさが別格なのです。
灸は雨が降ると悲しかった。向うの山が雲の中に隠れてしまう。路(みち)の上には水が溜った。河は激しい音を立てて濁り出す。枯木は山の方から流れて来る。
上記の文章は、あえて一文を短く区切り、短文を組み合わせています。そうすることで、テンポの良く、情景描写を連続させて、読者にスムーズに場面展開をイメージさせることに成功しているのです。
だらだらと一文を伸ばして美文を書こうとするよりも、潔く文章を区切って短文にする方が名文となるという良い例です。
横光利一は、このように文章を使いこなす名人であるのです。
翌朝灸はいつもより早く起きて来た。雨はまだ降っていた。家々の屋根は寒そうに濡れていた。鶏(にわとり)は庭の隅(すみ)に塊(かたま)っていた。
上記の文章は早朝の雨の情景を事細かに表現しています。
「いつもより早く」起きて来たと書くことで、いつもより早朝の時間帯であることを読者に伝えています。
雨はまだ降っていた
これは早朝でも「まだ」雨は降り続いていたという意味です。つまり、昨日から雨は一晩中降り続いていたということを読者に連想させるように仕向けているのです。
家々の屋根は寒そうに濡れていた。
上記の文章では家が「寒そうに」濡れています。人や動物は感情があるので寒そうにしますが、物に感情はないので、寒そうにはできないでしょう。しかし、あえて家を「寒そうに」することで雨の冷たさを表現しているのです。
この文章には雨という表現はありません。
それでも、読者はこの文章から冷たい雨に打たれた家の冷たさを知ることができます。その理由は非言語の世界の表現です。
「家々」が寒そうに濡れていたのではなく、「家々の屋根」が寒そうに濡れていたと書くことで、家々の屋根を濡らしている=雨が濡らしていると読者に連想させることができます。そして、家々が寒そうに「震えていた」のならば、これは「冷たい風」によって家々が震えていたのだと読者は連想することができます。
しかし、家々が寒そうに「濡れていた」ので、これは「冷たい雨」によって家々が濡れていたのだと読者に連想させられるのです。雨という言葉を直接使わずに、雨の情景を表現する。
これは読者に自ら連想させることで、小説の世界に引き込んでしまおうという横光利一が仕掛けた壮大なるレトリックでもあるのです。
鶏(にわとり)は庭の隅(すみ)に塊(かたま)っていた。
これは前の文章を受けての、一連のストーリーのシメになる部分です。
早朝から降り続いた家々が寒そうになるほどの冷たい雨の中で、「鶏(にわとり)は庭の隅(すみ)に塊(かたま)っていた」のです。
どうして、鶏が家の隅で塊(かたま)る必要があるのでしょうか?
ここでイメージしてほしいのが「おしくらまんじゅう」です。
バラバラになっていては寒いですが、おしくらまんじゅうのようにお互いの体を付き合わせれば、お互いの体温で体と体を温め合うことができます。家の隅ならば、隅にある壁の文だけ冷たい雨風をしのぐことができます。
この文はそこまでしないといけない雨の冷たさという雨の情景を描いているのです。
つまり、この文章でも「雨」という言葉を使わずに「雨」の世界を表現するという非言語の表現と読者にシーンを連想させて小説の世界に行きずりこんでいくというレトリックが使われているのです。
赤い着物の女の子は俥(くるま)の幌(ほろ)の中へ消えてしまった。山は雲の中に煙っていた。雨垂れはいつまでも落ちていた。郵便脚夫は灸の姉の所へ重い良人の手紙を投げ込んだ。
上記の文章は、バラバラのシーンを描いたのではなく、最初から最後まで一環したストーリーとしてつながった文章です。
赤い着物の女の子は俥(くるま)の幌(ほろ)の中へ消えてしまった。
上記の文章は、赤い着物の女の子が「俥(くるま)の幌(ほろ)の中へ消え」ただけではなく、車もまた消えてしまったことを意味しています。
山は雲の中に煙っていた。
こちらは「雲」と「煙」が同じような存在であることも意味しています。そして、山の中に「雲」が「煙」のようにさまよっている情景さえも表しています。つまり、一つの文章の中にいくつもの意味を重ね合わせることで芳醇かつ多様な世界観を作り出しているのです。
雨垂れはいつまでも落ちていた。
この「雨垂れ」も色々な意味を持っています。家の屋根から垂れ落ちる「雨垂れ」、雨に打たれる木々の葉から垂れ落ちる「雨垂れ」、人々の蓑から垂れ落ちる「雨垂れ」、そして天から雨として垂れ落ちる「雨垂れ」と、いくつものシーンがこの短い一文に詰まっているのです。
そのいくつものシーンを「いつまでも」と表現することにより、横光利一が作り出した雨の情景は一瞬のものではなく永遠に続くエンドレスな世界であることをも示唆しているのです。
郵便脚夫は灸の姉の所へ重い良人の手紙を投げ込んだ。
この文章になりますと、時代の違いのせいで、現代にはわかりにくい言葉が連続しています。
まず「郵便脚夫」は「郵便配達員」のことです。良人は「夫」のことです。
「重い良人の手紙」という言葉にはいくつもの意味が含まれています。
「重い手紙」は「(兵隊の)死亡通知」のことです。
それを「良人の重い手紙」と書かずに、あえて「重い良人の手紙」と書いたのには理由があるのです。
重い(絆で結ばれた)良人の手紙、重い(心に重荷になっていた)良人の手紙など、読者に自ら連想させることで、読者自身にこの小説の世界を買いたくさせていくという役目を持った一文であるのです。
- メディアKindle版
- 作者横光 利一
- 発売日2012-09-27